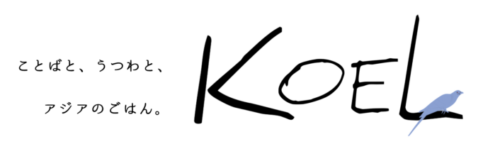Damian D’Silvaシェフ インタビュー

シンガポールは、建国50数年の若い国である。そこに伝統料理はないと思う人もいるかもしれない。しかし、シンガポール人の祖先たちが食べていた料理の多様性は、ちょっと想像するだけでも相当に豊かだ。北緯一度の小さな島に住んでいた人々と、各地から渡ってきた人々。さまざまな要素が混じり合って花開いた食文化は、その後の発展の中でどのように変化していったのだろう? シンガポールのヘリテージフードについて、その再現に心を尽くすダミアン・ディシルヴァさんにお話をうかがった(2020年1月取材)。
「忘れられた食材」とは?
「これ、何だか分かりますか?」ダミアンシェフの手に乗っていたのは、じゃがいものような食材。「匂いを嗅いでみてください」と言われ、鼻に近づける。熟したマンゴー?ジャックフルーツの香りをもっと豊かにしたような・・初めてなのになんだか懐かしい南国の香り。なんだろう?

「これはビンジャイの実です。シンガポールのヘリテージフードには欠かせない食材ですが、市場にはないので、シンガポール人に見せてもほとんどの人が知らないというでしょうね」
ビンジャイ(Binjai)はマンゴーの仲間で、独特の香りとさわやかな酸味があり、すりおろしてサンバル(辛味調味料)に入れ、魚の揚げ物などに添えるのが定番。子どものころにはあちこちに生っていたのに、今では手に入れることが困難になってしまったとダミアンシェフは嘆く。「こういった食材は、シンガポールの大切な遺産です。しかし、それらは守られることなく、徐々に失われつつあります。みんなホーカーセンターの料理には詳しいのに、ヘリテージフードには目を向けようとしない。寂しいことです」
一般的に、シンガポールの料理といえば、真っ先に紹介されるのがホーカー料理ではないかと思う。しかし、ダミアンシェフは「ホーカーセンターの料理はヘリテージフードとはいえない」と言う。「チキンライス、チリクラブ、ペッパークラブ・・・。人気の食べものは、どれも比較的新しい料理です。料理人だった祖父のレシピには、およそ200年前のものもあります。シンガポール料理の起源を振り返り、忘れられた調理法やレシピを復活させ、過小評価されている食材や調味料とともに、きちんと後世に残していきたいのです」
ヘリテージフードへの熱い思いからシェフの道へ
現在、レストラン・キンの厨房を率いるダミアンシェフは、ユーラシアンである父親とプラナカンの母親の間に生まれ、母方の祖母のプラナカン料理と、マラッカ出身の料理人だった父方の祖父の味で育った。「祖父の友だちには客家料理や広東料理を作る料理人もいて、彼らが家に来たときに手伝うことはありました。しかし、祖父自身はキッチンに誰も入れない人でした」

彼が祖父のキッチンに初めて入ったのは、11歳のある日のこと。「作り方を知りたいという私を、『見るだけだぞ』と招き入れてくれました。おそらく祖父は、私がどれだけ料理に興味があるかを試したのでしょうね。おしゃべりはいっさい許されず、ただ見るだけ。それでも私は興奮しました。タマネギがさまざまな形でカットされるのを見て、どうして違う包丁の入れ方をするのだろう?と不思議に思ったのを今でも覚えています。祖父がこのような機会を持たせてくれたことをとても感謝しています」 そんなダミアン少年だが、選んだ職業はエンジニア。料理の道に入ったのは40歳を過ぎてからのことだ。その転身の裏に、シンガポールのヘリテージフードについての熱い思いがある。
職人が作るものは、守らないと消えてしまう
「料理人としての私の使命は、祖父や祖母の味をきちんと理解し、伝えていくこと。祖父は、中国料理、マレー料理、インド料理、ユーラシア料理を巧みに調理し、祖母は、シンガポールで最も手の込んだ多彩なプラナカン料理を作ると自負していました。だから、レシピを勝手に変えることはいっさいありません。そのまま再現しています」。その多くは、シンガポールという国ができるずっと前に生まれた料理だという。たとえレシピは残っていても、その当時の味を再現するのは簡単なことではないはず。材料はどのように入手しているのだろう。そして、アレンジは少しも加えることはないのだろうか。 「確かに食材にはとても気を使います。シンガポールは土壌が豊かではないので、ここで手に入る野菜はベストな選択とはいえないのですが、それでも私は最高の食材を求めて常に歩き回っています。 レシピに手を加えることはしませんが、ひとつだけ変えていることがあります。野菜の切り方です。これはレシピをよりよく生かすための方法だと思っています。なので、もし祖父や祖母が知っても、たぶん怒りはせず『同じ味だね、ダミアン』と言ってくれるでしょう」
ヘリテージフードを再現するためには、伝統的な製法で作られた調味料も重要だ。「たとえば福建料理に使われる醤油。シンガポールでは良質の大豆は栽培できませんが、すばらしい醤油の作り手はいます。生産量はとても少なく、大量生産のメーカーには太刀打ちできませんが、とても品質のよい醤油です。トップは70歳、彼が引退したら職人気質の醤油は消えてなくなってしまうでしょう。私はそれをとても恐れています。私は彼に『あと2年だけ待ってください、醤油の作り方を学びたい』と伝えているほどです。 職人が作るものは、守らないと消えてしまいます。消えてしまった文化は二度と戻らない。だから私はあえて大きなメーカーではなく、職人が作る調味料を使い続けています」 さて、それではこの日実際にいただいた料理をいくつか紹介しよう。
Chi Pow Kai 纸包鸡(ペーパーラップチキン)

最初に登場したのがこちら。マリネした鶏肉を紙に包んで揚げる“ペーパーチキン”なのだが、今まで食べてきたものと全く違う。まず、その美しさに感動する。「これは、意味のある包み方なのですよ。今はほとんどの店で紙をホチキスで止めています。でも、それではどうしても油が中に入ってオイリーになってしまう。紙の止め方さえきちんとしていれば、油の温度でうまく蒸され、最高の状態で食べることができます」。ペーパーチキンといえばシンガポール、というイメージが強いが、紙に包んで揚げるという調理法は広東の料理人が伝えたものらしい。
Daun Pegaga (ツボクサのサラダ)

「ダウン・プガガ」。そう聞いても最初はまったく分からなかった。シェフは和名も聞いたことがあるらしく、一生懸命思い出そうとしている(彼はかなりの日本通)。スマホの存在も忘れ、連想ゲームのような会話が続くうち「ゴッコラ」という単語が登場。そうか、ゴツコラ!ツボクサのことだ。マレー系のユーラシアンスタイルの料理に使われるというが、シンガポールでこの葉を食べるのは初めてだ。舌触りのよい食材ではないが、これを細かくカットしてテクスチャーをより豊かにしているところがダミアンシェフ流。このダウン・プガガも「忘れられた食材」となりつつあるという。
Babi Masak Assam(豚肉の煮込み)

こちらは中国系プラナカン料理のひとつ。babi=豚肉、masak=煮込み、assam=酸味。タマリンドの酸味がきいた豚肉の煮込みで、その味付けは家庭によってさまざまだ。ダミアンシェフのバビ・マサック・アッサムは、マスタードグリーンの漬物(咸菜)と、生のマスタードグリーンの両方を用うのが特徴。
Gulai(牛頬肉の煮込み)

とろけるような牛頬肉のグライ。「マジャパイト王国時代にインドの影響を色濃く受けたインドネシアの煮込み料理」とのことだが、ヒンドゥー教徒は食べない牛肉を使うところがユニークだ。シンガポールやマレーシアでは、それぞれのエスニックグループの間で、さらには社会の変化の中で、たくさんのグライが誕生したという。
Fishmonger’s Haul(魚の蒸し物)

この料理をいただく前に、味見をさせてもらったものがある。調味料に使っている味噌だ。しっかりとしたうま味があるが、日本の味噌とはどこか風味が異なる。その味噌と、日本の梅干し(!)、咸菜(青菜の漬物)で塩味を付け、生姜、ネギ、赤トウガラシなどとともに蒸されたマナガツオのなんと滋味深いことか。
Feng(臓物の煮込み)

臓物料理にも思い入れがあるダミアンシェフ。インタビューの最中に、博多のもつ鍋の話が出てきたので、前から気になっていたユーラシアン料理の「フェン」をリクエスト。豚をまるごと使うのが伝統的なレシピだそうだが、肺だけは現在どうしても手に入らないとのこと。内臓の下処理にたいへんな時間がかかるうえ、3日間ほどかけて煮込むという手の込んだ料理だ。ユーラシアンのクリスマスに欠かせない料理で、数日前から準備を始めるという。
Dessert Sampler(スイーツ盛り合わせ)

右はスージーケーキ。ユーラシアンのお祝いに欠かせない、セモリナ粉の焼き菓子である。左はプラナカン菓子のクエ・ブンガ。真ん中のココナッツがたっぷりかかったものはクエ・コスイ。「スージーケーキは祖父、クエ・ブンガは祖母、クエ・コスイはおばのレシピ」だという。すばらしい共演!
それぞれの家庭にある伝統の味
さて、ここまでの料理を見ただけでも、さまざまな国やエリアの影響や融合があることが分かると思う。東南アジア、中国、インド、ヨーロッパ、それらが混じり合って進化したプラナカンやユーラシアンのお料理。どこまでをシンガポール料理と呼ぶのかは、さまざまな議論があるだろう。しかし、シンガポール人であり、プラナカンとユーラシアンの血を引くダミアンシェフが家族から受け継いだレシピは、間違いなくシンガポールのヘリテージフードといえる。
昨年末、シンガポール国立博物館で行われたイベントの動画で、ユーラシアンのクリスマスパイを作りながら、ダミアンシェフがこんなふうに子どもたちに問いかけるのを見た。「自分が何者か知らないのはとても悲しいことだと思う。我々は自分が何者かを忘れてはならない」と。 「シンガポールは、民族の違いを超えて『シンガポール人である』というアイデンティティのもとに発展してきた国ですが、それだけに、誇るべき違いまで見失うことがあります。その忘れがちな意識を、料理を通して引き出したいのです」
建国56年という若さのシンガポール。しかしその祖先たちの味覚の遺伝子は、一人ひとりのシンガポーリアンの中に生きている。それぞれの家庭の、それぞれの味の再発見。ダミアンシェフのお料理はその扉を開く原動力になるに違いない。
取材・文・写真:高島系子
取材協力:加藤晃子、伏見郁美

Restaurant Kin Straits Clan Lobby, 31 Bukit Pasoh Rd, Singapore 089845
関連記事はありません