真珠旅に鳥羽は外せない。初めての訪問は2022年の秋。青い海を見ながらアコヤ真珠の歴史と盛衰に思いを馳せる旅。
■品格ある昭和
なんて愛されているんだろう、真珠。鳥羽は心からそう思える場所だった。東京とまったく違う時間が流れている。タイムトリップではなく異次元トリップ。清く正しい、品格ある昭和。それもそのはず、19世紀、世界の真珠の常識をくつがえした「養殖真珠」が生まれた場所なのだから。

鳥羽駅でホテル行きのシャトルバスに乗り込もうとすると、「荷物だけお預かりすることもできますよ」と運転手さんから声がかかる。「夕方になるとどこも閉まりますからね。時間がもったいないでしょう」とニコニコ。ちょっとびっくりしたけれど、実直を絵に描いたような運転手さん、荷物だけ預けてそのまま博物館に向かうことにした。
数時間後、ホテルにチェックイン。もちろん荷物はたいせつに保管され、たいへんに紳士的なホテルマンがあれこれ案内してくれる。人数は多いのに圧迫感なく、控えめなのに親切。なんだろう、この温かさ。こんな接客を受けるのは久しぶりだ。
ホテル内の渡り廊下を歩いていると、すばらしい伊勢型紙を発見。興奮状態で写真を撮っている私たちに、高齢のご婦人から声がかかる。「あのう、よけいなことなんですけどね、あちらにずっと歩いていきますとね、エリザベス女王がいらっしゃったときのお写真がありますのよ。昭和天皇と美智子さまのお写真も。わたくし、感動いたしましてね。ぜひ見ていらしたら、と思いまして」なんてすてきな声がけなんだろう!
失礼ながらたいして調べもせずに予約したホテル、お値段も高いわけではないので、部屋の広さ以外はとくに期待していなかったのだが、もうここまでの間で大満足。エリザベス女王の訪問先に鳥羽があったことは知っていたけれど、まさかこのホテルだったとは。当時の写真を見ながら昭和に思いを馳せる。

真珠が輸出産業の花形と呼ばれた時代。ピークは1960年代で生産量の8割は海外に運ばれていったという。日本でふつうに暮らす人にとって真珠はまだまだ高嶺の花だった。70年代に入るとさまざまな事情で輸出の節目を迎え、その結果国内の需要が増えることになったらしい。「冠婚葬祭に真珠」と言われるようになったのはたぶんこのころなのだろう。それまではハレの日ほど着物の人が多く、真珠の出番も少なかったはず。いずれにしても、庶民が真珠を身につけるようになったのは比較的最近の話なのだ。
■小さな珠に孔を開けるインドの技術
真珠といえば日本。そう言われるようになったのも、じつはそう昔のことではない。その歴史は1893年(明治26年)この鳥羽から始まった。御木本幸吉氏の登場である。世界の真珠市場をがらりと変えることになったいきさつをちゃんと知りたくて、まずは真珠博物館に向かう。真珠が生まれるしくみや養殖法について1階で学んだあと、天然真珠のアンティークジュエリーを数多く所蔵する2階の展示室へ。
最初の展示は・・おおっ、ペルシアに続いてインド!である。「ボンベイ・バンチ」。インドの技術。どんな小さな珠であろうと孔を開ける職人がいた19世紀のボンベイ(ムンバイ)。キャプションによると、「インディアン・ローズウッドの木を輪切りにした台に真珠を打ち付けて固定し、弓錐を操作して孔を開けます」。農閑期の男性の仕事で、一人前になるまでに8年かかるという。こうして孔を開けて束にされてイギリスに運ばれたのがボンベイ・バンチというわけだ。

古来インドは天然真珠の産地だった。しかし真珠が採れたのは南インドのコロマンデルエリア。ボンベイはあくまで集積地、日本で言えば神戸のようなものである。なぜボンベイなのか?については勉強不足でまだよく分からない。これから調べていこう。
というわけで、養殖真珠の歴史を学ぶつもりが、すっかり心はインドに。なお、日本の真珠養殖の歴史も興味深いことがたくさん分かったので、この話はまた別の機会に。
■「ドーマン・セーマン」はどこから?
ところで。鳥羽には海女さん文化がある。これは世界的に見ても珍しいことなのだそうだ。展示にあったのも半裸の男性が海に潜っている写真ばかり。「真珠の世界史」(山田篤美著)によると、もともとこのエリアは伊勢神宮にアワビなどを奉納するため、海女文化が浸透していたという。であれば、真珠が海女さんの仕事になったのは自然な成り行きだったのだろう。真珠採りの季節は真冬。相当に過酷な仕事だったと思われる。

そんな海女さんたちを守り続けてきた魔よけのモチーフががあるという。「ドーマン・セーマン」、なんとも不思議な響きである。しかもマークは九字紋と五芒星。これはきっと海の向こうから伝わってきたに違いない!・・などとまた別のところにスイッチが入る。
そんな空想の答えを探しに、またここに来よう。
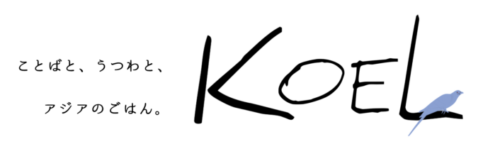





コメントを残す